Director's Statement
映画『Feel/Unfeel』 監督:北 宗羽介
『ノルマル17歳。』予想外の反響
映画『ノルマル17歳。-わたしたちはADHD-』は、脚本のメインを担当した神田凜さんの実体験を元に作った物語です。構成はシンプルながらも、ありのままの「現実」を描こうとしました。また予告編は、ショッキングな表現のシーンを軸に作ったため、もしかしたら当事者の方は辛すぎて観に来ないかもしれないという予感が最初ありました。
協力者の方がSNSで予告編を投稿したところ、ちょっとしたバズりとなり、ポジティブ・ネガティブ両方のコメントが数多く書き込まれました。少し荒れた状態となりましたが、「発達障害」に対する思いがこれほどあったのかと驚かされました。
東京での公開後、最初こそ俳優のファンの方たちが多かったものの、明らかに当事者や関係者の方(家族や教育・福祉・医療関係者)が多くなり、満席回も多く出ました。
多くの方々から、「とてもリアルだ」「これは自分でしかない」「こういったことを自分もしてしまっていた」という反応を多くいただきました。自分自身の経験に重ね合わせるのか、当事者の方などがものすごい号泣をされるのが伺えました。ストーリーがシンプルな故に、自分自身を投影しやすいのではないかと思います。多くの当事者の方がヘビーリピーターとなり、中には10回以上もご覧になった方もいらっしゃいます。
各地の映画館での上映が一段落した後も、医療・教育・福祉関係や自助会などの主催者様たちによる自主上映という形で広がり、公開からもうすぐ2年となります。いまだに自主上映のお問い合わせをいただいており、感謝の念に堪えません。
隠れた「現実」
各地での上映の反応を見て、予想以上にこの映画が「リアル」なんだということを認識させられました。「この演出はやりすぎだったか」といったシーンでも、実はそれは過剰でも何でもなく、むしろもっと酷い現実がたくさんあります。
「できない」自分の子どもに対しての苛立ちが過剰な言葉や暴力となって現れる――多くの『普通の人々』がドラマや映画でしか見たことがないシーンが、実はどれだけ現実で行なわれているか。かつては「座敷牢」という物理的な隔離によって「家の恥」を隠していたものが、実はごく最近まで、いや現在進行形でもまだ行われています。ただ「表に出て来ていない」だけです。
映画はシンプルな構成ではありますが、実はとてつもなく「リアル」なので、ここまでの反響があるのかなと、感じています。これまで「隠されてきたもの」「あまり出て来なかったもの」がそのまま表現されている。だからこそリアルすぎて、(怖いけど)何度も観ってしまう――そして自分を昇華させているのかもしれません。
これは当初、「協調性」を重視する日本や東アジアで顕著な状況ではと考えていました。
しかし、映画公開前、海外の当事者の方々などにも観ていただいたところ、実はこれは他の国々でもそんなに変わらない状況だと分かりました。
「個人」を重視し、「多様性」の進んでいる欧米圏であっても、いざ「家族」の内部になると、日本とあまり状況が変わらないことが多いようです。
 | 
|
「感じない」「感じようとしない」
しかし、「何も感じなかった」というような方ももちろんいました。作品には好き嫌いがありますが、そういう類ではない感じのものがありました。
シンプルな物語の構成を、「テンプレート的な記号」以上に見なかった、という印象です。過剰な感情表現は、「実際にはあり得ない」「作られたドラマや映画の中での定形パターン」という受け止め方です。
この作品に携わる前、複雑なタイムリープものの脚本を3本ほど書いていて、パズルのように整合性を合わせていくことがメインのその「合理的な作業」に、どんどん「リアルな人間」から離れて行く感覚がしていました。
「現実」を描くのに、余計な「脳」をはぎ取ろう。シンプルな構成(=今まで「あたり前」ととらえられているもの)の中に、本作のテーマである「普通とは何か」そのものを入れてみよう。「ありきたりな普通」のストーリー(生活)が、実は「普通」ではなかったという「気付きの種まき」です。
東京公開時、アップリンクのメディア「DICE+」でのレビューで、うまく表現していただいていました。
『映画の中では、絶えず郊外と都市部が適度に共存する美しい街並みが映し出される。(中略)静かで美しい街並みの中に、生きづらさは潜んでいるのかもしれない。そう考えると怖い風景だ。』
しかし、気付かないことは、怖いことです。
シンプルなストーリーゆえに、それをこれまでの定形化した「側(テンプレート)」としてしかとらえず、分析・考察すべき点が「ない」と拒否してしまいます。
「伏線と回収」「誰かがついているウソ」「長大な説明」を考察する・解釈する・推察する・洞察するなど、『風の時代』を特徴づけるような「脳先行」の思考だけになり、リアルな「身体感覚」が失われているのが現代です。
養老孟司先生が「脳化」と表現したのは、もう20年以上前のことです。しかし、現代はSNSに代表される「脳化」が進むばかりです。
黒澤明の『生きる』パターンの作品(わずかな余命で生きる意味を知る)も、テンプレビジネス化されてしまっています。
前述の人たちは、そういうことにも敏感ですので、より「本物の人間の姿」を遠ざけているのかもしれません。
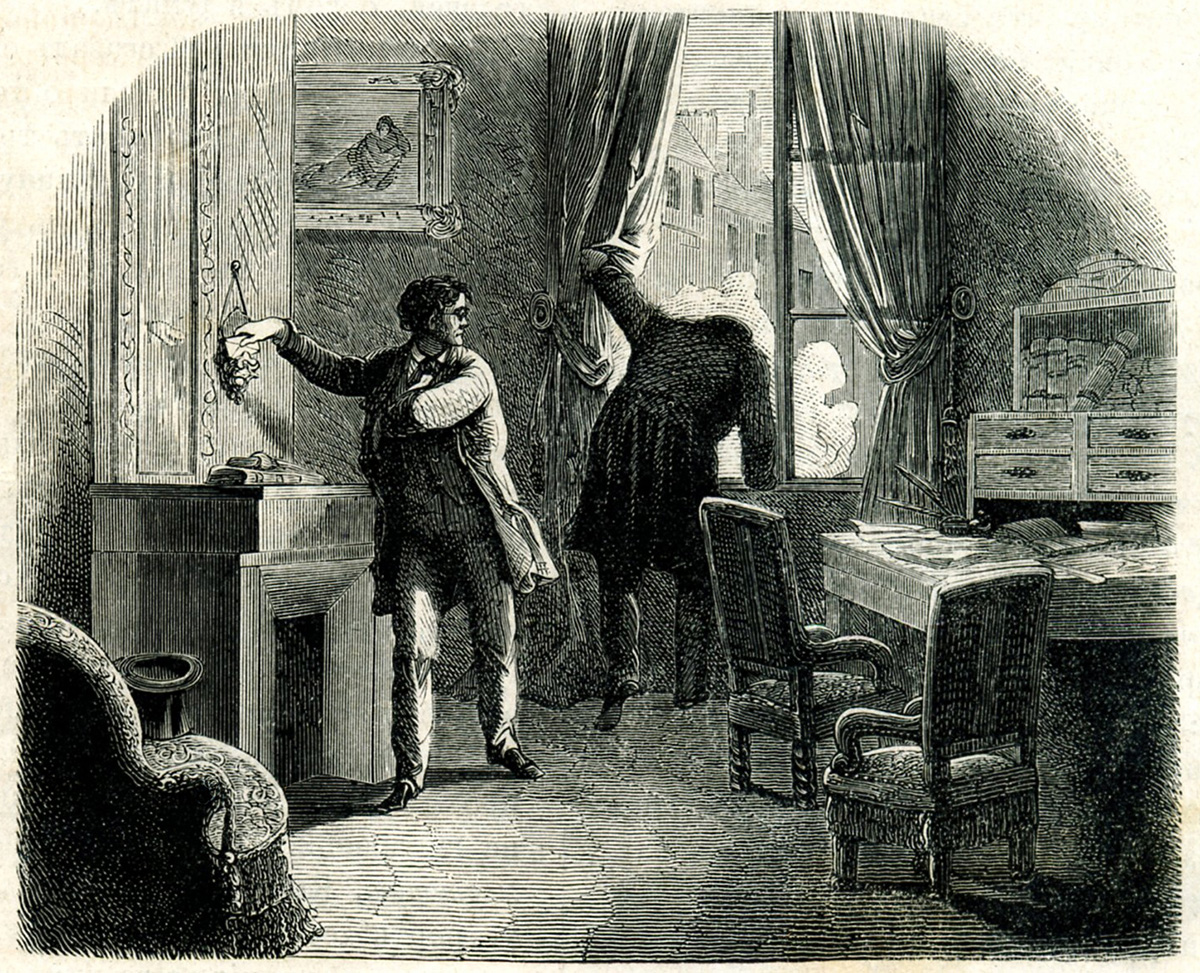
エドガー・アラン・ポーの『盗まれた手紙』は
この状況に似ています
(画像はフレデリック・リックスの挿絵)
「見ないようにする」「気付かないようにする」「感じないようにする」社会
「多様性」を重視しなさいと社会は投げかけて来ます。あからさまに差別をすると、「炎上」が起こり、法で処罰されることもあります。
なので、安全のために『見ないように』します。
電車やバスの優先席に座っていて、お年寄りや身体の不自由な人が来ても、寝たふりして「気付かないように」していればいいのです。万が一指摘されたら、「気付きませんでした」と言えば済みます。
「気付かない」ことが一番です。何よりも『感じない』ことで壁を作れば、自分の安全を保てます。
作品の内容と直結しない表現の技術的な部分を指摘しても、肝心な「人間が生きている」部分では「感じない」か「感じないふり」、あるいは「なかった」ことにします。
それは本当に感じていないのか、あるいは意図的(無意識的)に避けているのか。
この『感じない』『感じようとしない』状況が、発達障害をはじめ多くのマイノリティを避ける人たちの『静かなる分断』ではないかと感じます。
ただ関わらないようにしているだけならばまだ害はないでしょう。
見ているのに無視する、あるいは存在していないとする、その「視線」と「換言」こそが問題であり、<正しくあれ>と思いたい『普通』の土台となっているのではないでしょうか。

「感じないように」して身を守る
私たちは「棲み分け」られるのか
「共生」とは「棲み分け」ることで、無理に価値観の違う人たちが同じところで生きる必要はないでしょう。その「棲み分け」が出来ればいいのですが、今ではその小さな「棲み処」が消されようともしています。戦後の当時、小学生だったある方は、「特殊学級」というものが出来ることを知りました(今では「特別支援学級」として柔らかくなっていますが)。
何となくみんながそわそわし出したそうです。結果的に「ちょっと変わっている友達」が入れられることになり、それ以降ほとんど会わなくなったそうです。
今までは「ちょっと変わっている」だけだった人が、「特殊な人」になってしまったことで、その後、ずっとそのことが心に焼き付いていたということです。
「区別する」ことで、「人の心」が分断されてしまいます。
「発達障害」の人たちは、「空気が読めない」(感じることが出来ない)と言われます。
しかしこれは脳機能の問題で、「人に迷惑をかけたくないのにかけてしまう」結果につながってしまいます。
一方で、定型発達の人たちにも「空気が読めない」(感じない)人たちがいます。
これも個別で見れば細かなことがあるとは思いますが、ほとんどが「利己的」な理由でそうするのが多いのではないでしょうか。
多くの人は、後者の悪いイメージで前者も見てしまいます。
親鸞というお坊さんは、「悪人」こそが救われると説いています。
ここで言う「悪人」とは悪いことをする人ではなく、自らの煩悩・欲望を意識できる人・内省できる人のことです。
自分の中で「人に迷惑をかけたくない」と思いながらも迷惑をかけてしまうのと、そんなことを思いもしないで(意図的に)迷惑をかけるのとでは、前者が「悪人」となります。
この「悪人」こそ、救われるべき存在ではないでしょうか。
『ノルマル17歳。』の中では、映画『男はつらいよ』(寅さん)に出て来るような下町風の人々が出て来ます。彼らは、他者と付かず離れずの位置で、「いい感じ」で接して来ます。突っ込み過ぎず、また無視することもせず。これはかつての人情映画・人情ドラマの定形のパターンでもありました。
この「いい感じ」の距離感が、「共生(棲み分け)」感を生み出します。
彼らは主人公たちの発達障害のことを知らず、知っても「ありのままのその人」として接します。彼らは「脳化」しておらず、地に足の着いた生き方をしています。
だから彼らは、明らかに発達障害と見られる寅さんと共生できるのではないでしょうか。人に迷惑をかけてしまう寅さんが「悪意を持っていない」「利己的でない」ことを知っているからです。寅さんは「ちょっと変わった喧嘩っ早い人だけど、悪気のない良い人」だから、ある程度の距離ならいてもいい。寅さんは自分を知ってるので、人と近くなりすぎず、問題を起こしたら反省して旅にも出ます。
しかし、現代の「脳化」した人々は、寅さんを単に「迷惑系」として炎上させ、糾弾してしまうのではないでしょうか。
この「下町風の人々」こそ、「共生」のヒントではないかと思っています。
「まあまあ」と喧嘩の仲裁ができる人たち。これはネットの文字上では難しい。実際の「身体」があって、手を差し伸べて「まあまあ」とする「粋な人たち」。
今ではどっちが「論破」したかをジャッジしてより分断を煽ってしまうでしょう。
だからこそ「永遠のワンパターン」である寅さんを使ったのです。

かつての日本の人情映画パターンに「共生」のヒント
画像は『東京物語』(小津安二郎監督)より
ドキュメンタリー映画『Feel/Unfeel』
音や光に過敏すぎる特性を持っている方がいます。逆にそういった感覚が鈍麻な方がいます。発達障害でそういった感覚特性を備えていると、より生きづらさが増して行きます。「普通の人々」は、それを想像するのが難しいでしょう。ヘッドホンをして歩いている人を音楽を聴いていると思い、雑音を遮断するためと思うことはほとんどないでしょう。
そして、「発達障害」を「感じない」あるいは「感じないように」「気付かないように」静かな分断をしている社会。
映画『Feel/Unfeel』は、「感じる」「感じない」ということに軸を置いた、「発達障害」を取り巻く社会の問題を浮き彫りにするドキュメンタリー企画です。
明らかな『分断』が世界各地で進んでいます。
そして見えないところで、『静かなる分断』がそれに拍車をかけているようです。
「頭でっかち」で身体を失った社会は、感じることのないAIのようです。
いや、AIでさえ、「感覚」機能を付け始めています。
このまま人間とAIが入れ替わってしまうのでしょうか。
人間の行く先は、脳内に閉じ込められた映画『マトリックス』の世界かもしれません。
『皮脳同根』――受精卵が分裂して初期に、「外肺葉」という同じ層から、皮膚と脳が出来て行きます。皮膚と脳とは密接につながっていると考えられます。
脳と神経系はつながっていて、「脳」が単体で身体を制御しているのではなく、「第三の脳」とも言われる皮膚も働いているようです。従属的なセンサーとしてではなく。
『ニューロダイバーシティ』――脳や神経のつくりが個々で違う、「神経の多様性」の考え方から見れば、「発達障害」は、脳機能に問題があっても「身体」で対応している発現なのかもしれません。
逆に見れば、「脳化」した人々は、脳はあっても皮膚感覚が欠如した状態、つまり「発達障害」の逆パターンの状態であるとも解釈できるかもしれません。
私の全ての作品で共通するテーマは、『人間はいかにして生きて行くか』です。
『発達障害』の人も、『脳化』した人も、「まあまあ」となって、「中庸の人間世界」に戻って行くのが課題ではないでしょうか。(他のマイノリティでも同様です)
『ノルマル17歳。』は、より多くの人々に「発達障害」を取り巻く環境の実態を知っていただくきっかけとして、フィクション(物語)形式にしました。
『Feel/Unfeel』では、物語を超えて想像も難しい「ものすごい現実」と課題を映し出し、より多くの方々に「感じ」「考えて」いただけるようなきっかけにしたいと思い、ドキュメンタリー形式でまとめることにしました。国内外の多くの人たちに取材を始めています。
どうか多くの方々に本作の意図に共感いただき、制作へのサポートにつなげていただければ幸いに思います。どうぞよろしくお願い致します。
2025年9月23日 秋分
監督:北 宗羽介 / Director: Sounosuke Kita
|
Don’t think, feel! It is like a finger pointing away to the moon. Don’t concentrate on the finger, or you will miss all the heavenly glory. Bruce Lee “Enter The Dragon” 考えるな、感じろ。 それは月をさす指のようなものだ。指だけを見るな。天の光明を見逃すぞ。 ブルース・リー「燃えよドラゴン」より |
北 宗羽介 Sounosuke Kita
1970年生。映画プロデューサー・映画監督。幼少より漫画を描き、やがて特撮映画・アクション映画にのめり込む。学生時代は自主制作映画や演劇活動。広告代理店にて勤務後、独立起業。広告制作やIT関連に携わりながら、独立系映画の製作・配給、海外映画の撮影サポート等を行なう。「国際共同製作」を基本路線に、独自の映画製作・配給形態を作り上げて行っている。一方「日本の精神文化の美しさ」を追求していくため、女性だけの殺陣アクションチーム「凜派(RIN-PA)」を主宰し、国内外で活動を広げている。
映画『ノルマル17歳。-わたしたちはADHD-』(2023年/監督・共同脚本・プロデューサー)、『初恋』(三池崇史監督/2019年/製作委員会メンバー)、『自治の種まく人』(2013年/監督・プロデューサー/ドキュメンタリー作品)ほか
映画『Feel/Unfeel フィール/アンフィール《発達障害と日本》』(仮名)
ドキュメンタリー / 約100分予定/2026年初夏公開予定/国際映画祭参加予定
監督・プロデューサー:北 宗羽介 製作・配給:八艶合同会社
後援:NPO法人えじそんくらぶ、とりぷるADH (ほか後援・協賛交渉進行中)